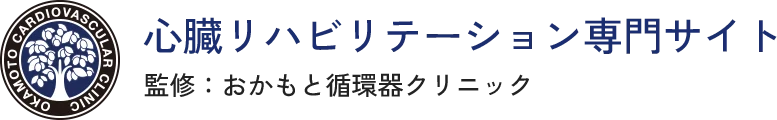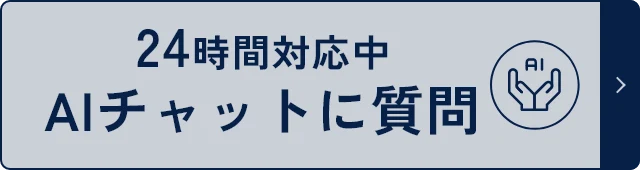CPXを活用した運動強度の設定
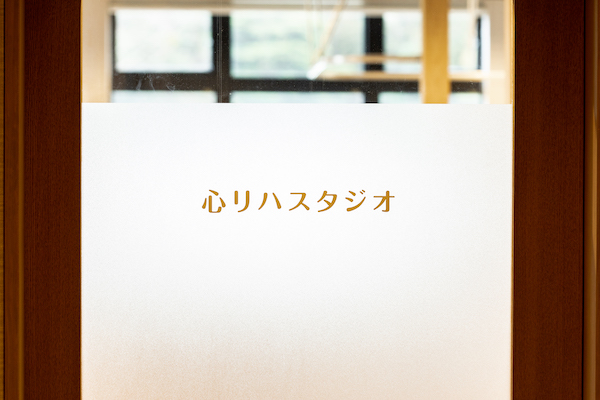 「運動療法は理学療法士や健康運動指導士が行うもの」と思われがちですが、実際には心臓リハビリテーションの重要な一部です。そのため、心疾患患者さんに関わる医師や看護師、運動指導者など、多職種が適切な運動処方について理解しておくことが大切です。
「運動療法は理学療法士や健康運動指導士が行うもの」と思われがちですが、実際には心臓リハビリテーションの重要な一部です。そのため、心疾患患者さんに関わる医師や看護師、運動指導者など、多職種が適切な運動処方について理解しておくことが大切です。
運動処方とは?
 運動処方とは、患者さんの健康状態や運動耐容能を評価し、安全で効果的な運動プログラムを設計することを指します。心疾患患者さんにとって、適切な運動は再発予防や生活の質の向上に役立ちますが、負荷が大きすぎると心臓に過度な負担をかける可能性があります。一方で、運動不足も筋力低下や心肺機能の低下を招くため、バランスの取れた運動が必要です。
運動処方とは、患者さんの健康状態や運動耐容能を評価し、安全で効果的な運動プログラムを設計することを指します。心疾患患者さんにとって、適切な運動は再発予防や生活の質の向上に役立ちますが、負荷が大きすぎると心臓に過度な負担をかける可能性があります。一方で、運動不足も筋力低下や心肺機能の低下を招くため、バランスの取れた運動が必要です。
CPXを活用した運動強度の決定
CPXを活用すると、患者さんごとに最適な運動強度を科学的に設定できます。特に、**嫌気性代謝閾値(AT:Anaerobic Threshold)**を指標にする方法が一般的です。
低強度(AT以下)
心肺機能の改善や、日常生活の活動レベル向上に適している。
中強度(AT付近)
持久力を向上させ、心血管リスクの低減に役立つ。
高強度(AT超え)
運動パフォーマンスを向上させるが、心疾患患者さんには負担が大きく注意が必要。
ATレベルの運動処方は、心臓に過度な負担をかけることなく、効果的なトレーニングを可能にします。
すべての患者さんがCPXを受けられるわけではありません。その場合、以下の方法を用いて運動強度を設定します。
簡易心拍処方
最大心拍数の一定割合を目安にする
自覚的運動強度(RPE)
患者さん自身の感覚を基に運動負荷を調整
トークテスト
運動中に会話ができる程度の強度を維持
これらの指標を活用することで、CPXが利用できない環境でも、個々に適した運動処方を実施できます。
運動を継続するための工夫
運動処方が適切でも、継続できなければ効果は期待できません。患者さんの生活スタイルに合った方法を提案することが重要です。
運動を継続するためのアイデア
- ・目的地の1駅手前で降りて歩く
- ・階段を利用する
- ・買い物を徒歩で行う
- ・運動記録をつける
- ・仲間と一緒に取り組む
無理なく継続できる運動習慣を作ることで、心肺機能の向上や健康維持に役立ちます。